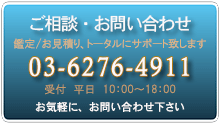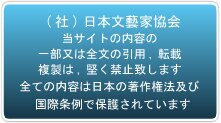【ニュースコラム】
検察事務官手記:長男亡くし被害者の立場から捜査求める
|
交通事故で長男を亡くした神戸地検検察事務官、三浦良治さん(56)が、警察・検察に被害者の立場に立った捜査を求める手記を毎日新聞に寄せた。
現職の検察事務官による手記の公表は極めて異例だ。
長男宏文さん(当時21歳)は宮城教育大2年だった99年11月17日、仙台市内でバイクに乗って帰宅中、市営バスと正面衝突して死亡。
宮城県警はバイクが中央線を越えたとして、宏文さんを道交法違反容疑で書類送検。仙台区検は容疑者死亡で不起訴とした。
事故翌日、仙台中央署の警察官は「バスの運転手は検察庁に送らない。息子さんを道交法違反で送検する」と、遺品を受け取る三浦さんに言った。
息子の死を知ったばかりなのに、捜査を終えて罪名も決まっていることにがく然とした。
事故の3日後、自宅に来たバスの運転手は「バイクと並んで走る車があった」と説明。
三浦さんは、この車が事故に関係しているとみて警察官や担当副検事に話したが、取り上げてもらえなかった。
何度も仙台に足を運び、新聞の折り込み広告で目撃者を捜したが、有力情報はなかった。
03年、事故の真相を知るため、バスの運転手を相手に損害賠償訴訟を起こしたが敗訴。
04年には「不適切な捜査で精神的苦痛を受けた」と国などに賠償を求める訴えを起こしたが、これも訴えを退けられた。
三浦さんは89~00年、3000件以上の交通事故捜査に携わり、うち2000件が略式起訴。
その経験も踏まえ「事故捜査は本当にこれでいいのかを問うことが、子を失った親の使命」と話している。
【山田英之】【毎日新聞 2006年8月27日 3時00分】
■事務官手記要旨
長男宏文が、教師になる夢を果たせないままこの世を去って、もうすぐ7年を迎えます。
「交通事故捜査はこれでいいのか」との思いが、いまだ頭から離れません。
国家賠償訴訟で息子の事故でどのような捜査が行われたかを問いましたが、私が望んでいた捜査関係者の証言は得られず、門前払いで終結しました。
息子の死を忘れるため、私はあえて多忙な大阪地検刑事部を希望して転勤、その後、大阪地検特捜部にも勤務しました。
仕事の合間に四国遍路に出かけ、交通事故捜査はこれでいいのかを自問自答しました。
「一人の父親になろう」と決心し、宮城県警と国を相手に訴訟に踏み切りました。
自らの職場も訴えるのですから悩みました。
法務省は被害者に配慮して、一定の条件を満たした場合、これまで原則不開示にしてきた供述調書を開示することになったと報道されました。
しかし、私の裁判では、刑事訴訟法47条(訴訟書類の非公開)によって、目撃者調書の提出を拒否されました。
どのような捜査資料で相手の運転手に過失がなかったと判断したのか、知ることができませんでした。
検察審査会に申し立てる手段もありますが、警察が死んだ者を容疑者にしているため、この制度を受けることもできません。
多くの交通事故遺族が、どんな事故だったのか分からずに無念のまま泣き寝入りしているかと思うと、どうしても息子のような事故処理をしてほしくありません。
交通事故で家族を失った遺族が唯一、事故状況を知り得るのが実況見分調書です。
せめて、遺族に見せてくれる事を望みます。
そして、法務省、警察庁には被害者の立場に立った捜査と、人の「命の重さ」「家族の悲しみ」を今一度、考えていただくことを望みます。
|

神戸地検検察事務官、三浦良治さんの、この勇気ある行動に拍手を贈りたい。
弊所に寄せられる交通事故の相談で圧倒的に多いのが
残念ながら「警察・検察に対する事故捜査の不信感」なのである。
複雑で多忙な交通事故捜査であるのは承知しているところだが、
中には稚拙な捜査や思い込みによる間違った判断している事件も目にすることがある。
科学捜査技法がどれほど進化しても、
エラーの存在を疑い再確認の必要性を忘れてならない。
交通事故に関わった人々が、どれほど苦しめられているのか、
これを機会に猛省していただきたい。
(2006/09/02山崎)
![]()